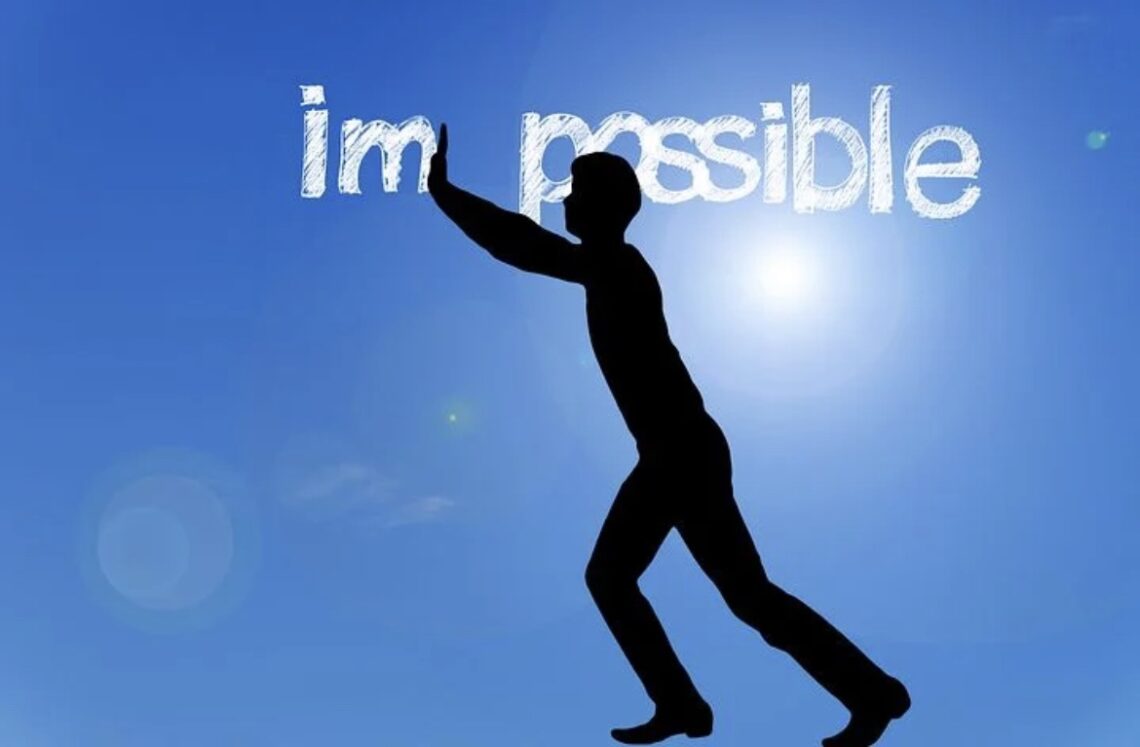
心理学|ピグマリオン効果|期待をやる気に、そして結果に
みなさん、こんにちは。
Ysです。
今日も心理学、「ピグマリオン効果」について書きます。
ピグマリオン効果とは、人々が他人に対して持つ期待が、その人の実際のパフォーマンスに影響を与える心理現象のことを言います。
つまり、私たちが他人に対してポジティブな期待を持つと、その人は期待に応えようとして、実際に良い結果を出すことが多くなります。逆に、ネガティブな期待を持つと、その人のパフォーマンスが低下することがあります。
ピグマリオン効果の身近な例をいくつか挙げてみます。
学校の先生と生徒の関係
先生が生徒に対して、「この子は頭が良い」「勉強が得意だ」と期待して接すると、その生徒は自分に自信を持ち、実際に勉強成績が向上することがあります。逆に、「この子は苦手だ」と思われると、生徒は努力する気力を失い、成績が下がることがあります。
職場での上司と部下の関係
上司が部下に対して、「この人は仕事ができる」と期待すると、部下はその期待に応えようと努力し、実際に仕事の成果を出すことがあります。逆に、上司が部下に対してネガティブな期待を持つと、部下は自分の能力を疑い、仕事の成果が出にくくなります。
家庭での親子関係
親が子どもに対して、「この子は何でもできる」と期待を持つと、子どもは自分に自信を持ち、様々なことに挑戦しやすくなります。しかし、親が子どもに対してネガティブな期待を持つと、子どもは自分の能力に自信を持てず、挑戦することが苦手になることがあります。
このように、ピグマリオン効果は、私たちが他人に対して持つ期待が、その人の行動や成果に影響を与えることを示しています。私たちの期待は、他人の自信や努力に大きく関与しており、ポジティブな期待を持つことで、良い結果が得られる可能性が高まるということですね。
相手の良い所を見つけることを心がけることがそれが期待になり、ピグマリオン効果によって更に良い関係になるかもしれないですね。
ピグマリオン効果を理解することで、私たちは自分自身にもポジティブな影響を与えることができるのではないでしょうか。自分に対しても高い期待を持ち、自分を信じることで、自分自身のパフォーマンスも向上させることができます。まさに自分を信じるで「自信」ですね。
ただ、過剰な期待はプレッシャーになり、期待に応えられなかった時に失望に変わったりとマイナスの側面もあるかもしれません。そのような側面にも意識しながら、バランスよくポジティブな人間関係を築き、自分と向き合えると良いですよね。
今回も読んで頂きありがとうございました。



