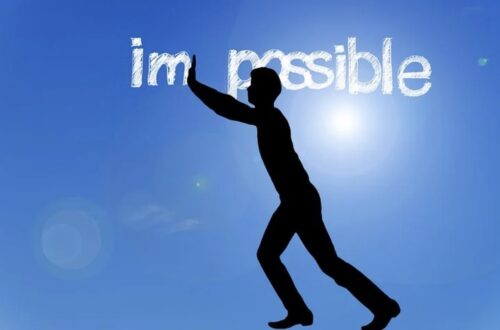【教育】非認知能力|これからの時代を生き抜く力|身につける方法
みなさん、こんにちは。Ysです。
今回は「非認知能力」についてです。
「非認知能力って何?」
「身につくとどうなるの?」
「身に付けるにはどうすれば良いの?」
と気になりますよね。
興味あればぜひ読んでみてください。
非認知能力とは
- 認知能力以外の能力(認知能力とは知能検査、テストで計測できる力のこと)
- 勉強だけでは身に付かない
- 「意欲」「興味・関心」「粘り強さ」「協調性」など
「認知能力以外の能力全般」つまり「テストで測ることができない力」です。「塾や学校の勉強だけでは身につけるのは難しそう。でも社会に出れば必要な能力だ。」って思いますよね。小難しい説明をしなくても、必要だということは直感的にもわかると思います。
そんな非認知能力についてもう少しその特徴をまとめていきます。
非認知能力の特徴
- 生まれ持った気質や性格ではなく後天的に身に付く「スキル」
- 特に幼少期の環境や保育者とのコミュニケーションと深く関係
- 認知能力と非認知能力は相互に絡み合い相乗効果で育まれるもの
調べてみると非認知能力に関する書籍や論文が国内外で多数出ていました。世界的にも注目されているようです。日本でも文部科学省の資料にその重要性が示されていました。
なぜ、それほどにも注目されているのでしょうか。
「後天的」「幼少期が大切」「認知能力との関係性」がポイントのようです。
先天的なものだったら諦めがつきますが、後天的なものなら身に付けておきたいですよね。いつでも身に付けられるなら慌てる必要もないですが、幼少期が重要なら機会を逃したくないですよね。(でも、幼少期にしか身に付けられないわけではないそうです。)
また、非認知能力を高めると認知能力も高めやすいそうです。理由は「興味、関心、意欲が高いと勉強にも興味を持って粘り強く取り組める」から。つまり「好きこそ物の上手なれ」ということ。
さらに面白いのは「認知能力が高いと非認知能力を向上させやすくなる」ということです。認知能力が高いと発想の幅を広げたりより深く考えられるようになるからですね。
「他の能力とどう関係しているのか」「幼少期にどのような教育をすれば良いか」という関心があるからこそ、研究テーマになり、本になるんでしょうね。身に付けない理由、注目されない理由がもう見つかりません。
ではあとは「どうやって身につけるのか」ですね。
あともう少しお付き合いください。
身につけるには
- 意欲や関心を高めるために子供が面白いと感じるものを用意する。
- 子どもが自分で発想し考えるようなコミュニケーションを取る。
- やることの内容そのものや結果よりも取り組む姿勢に注目してあげる。
非認知能力の身に付け方については様々な記述がありました。
が、結局は
「豊かな環境を提供する」
「子どもが自分で考えることを促す」
「取り組む姿勢に注目する」
の3つでした。以降説明していきます。
まずは「豊かな環境を提供する」についてです。
「豊か」とは金銭的にという意味ではなく、子どもが自由に発想できるような「遊び道具」をふんだんに用意してあげること。文字通りのおもちゃや教材も良いですがそれに限らないそうです。確かに与えられたおもちゃだけでは満足せず、目の前にある全てのものが興味・関心の対象になっていますよね。日本はこれまでも子どもの自由な発想を尊重し育む教育方針が浸透しているので、この内容は目から鱗というほどでもなさそうです。
次は「子どもが自分で考えることを促す」についてです。
子どもが何かに取り組んでいるとき、大人の正解を押し付ける必要はないそうです。
大切なのは自分なりに考えること。
考えて試してみて、上手くいったり失敗したりして学ぶそうです。
つい大人では思いつかないようなことをしようとしているとき、手を差し伸べたくなりますよね。
限定的な命令や正解を教えるのではなく「じゃあどうしようか。どうしたら良いかな」など問いかけてあげるようなコミュニケーションが良いそうです。
最後に「取り組む姿勢に注目する」です。
もしかするとこれが一番見落としがちかもしれません。どうしても行動の結果にばかり注目して「良い、悪い」「偉い、偉くない」と決めたくなりますよね。良い結果に対して褒めてあげることが悪いとは思いません。ですがこれでは子どもが大人の価値基準に合わせようとしてしまうようです。怒られないように、褒めてもらうために、空気を読み、大人が求める正解を探してしまうんですね(本当にダメなことはダメだと言わないといけないですが)。
では、そうならないようにはどうすれば良いか。結果に注目せず、取り組む姿勢と過程に注目してあげること。つまり、主体性やチャレンジ精神そのものを見てあげるということ。
終わりに
いかがでしたでしょうか。
ググれば似たような情報は出てくるかもしれませんが、私なりの学びとそのまとめをきっかけにより深く知りたいと関心を持った方が一人でもいれば幸いです。
私自身も今回の投稿をきっかけに非認知能力に対する関心が高まり、もう少し勉強したいなと思うようになりました。
最後に必ず受けるであろうツッコミに対して、先に自ら言っておきたいと思います。
「筆者は独身で子どももいないのになぜ教育に関する内容を投稿しているのか?」
その通りです。先日姪っ子と遊んだ時、自由に無邪気に遊んでいる彼女を見てこの「非認知能力」というキーワードを思い出し、気になったので少し調べてみたのでした。
最後まで読んでいただきありがとうございました!